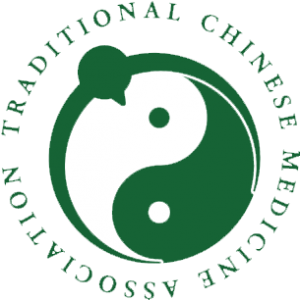銀翹散
体質:寒邪による発熱
寒邪は中医学で外因の一つとされ、寒さや冷えによって体に侵入します。寒邪が引き起こす頭痛は、悪寒(寒気を感じる)、発汗がない、四肢の冷え、鼻水(透明でサラサラしたもの)が出る、頭が重く感じるなどの症状を伴います。これらは「風寒表証」と呼ばれる状態で、寒邪による外感症状に該当します。
おすすめ処方:銀翹散
銀翹散は本来、風熱感冒(熱を伴う風邪)の初期に使われる処方ですが、その配合成分には一部、寒邪を追い払って発汗を促す効果があるため、寒邪が体内で熱化した場合にも用いることができます。以下に処方の構成生薬とその役割を解説します。
生薬とその効果
1. 金銀花(きんぎんか)
→ 清熱解毒(熱を冷まし毒を解く)作用があり、外邪を排除します。抗炎症・抗菌効果も期待されます。
2. 連翹(れんぎょう)
→ 熱を冷まし、腫れを抑え、外邪を取り除きます。のどの腫れや痛みに効果があります。
3. 荊芥(けいがい)
→ 発汗作用を促し、風邪による頭痛や悪寒を緩和します。
4. 薄荷(はっか)
→ 外邪を追い払い、頭痛や鼻づまりを改善します。体をさっぱりと整えます。
5. 牛蒡子(ごぼうし)
→ のどの腫れや痛みを和らげる効果があり、解毒作用も持ちます。
6. 淡豆豉(たんとうし)
→ 軽い発汗を促し、寒さと体の内側の熱を調整します。
7. 桔梗(ききょう)
→ 気道を開き、のどを楽にし、痰を取り除きます。のどの痛みにも有効です。
8. 甘草(かんぞう)
→ 諸薬を調和し、のどの炎症を鎮めます。緩和作用を持つ重要な生薬です。
9. 芦根(ろこん)
→ 熱を冷まし、乾燥による渇きを和らげます。
10. 竹葉(ちくよう)
→ 熱を冷まし、軽い炎症や不快感を和らげます。
適応と使用方法
適応
寒邪による頭痛、寒気、鼻水(透明でサラサラしたもの)
体内で寒邪が熱化し、のどの痛みや軽い熱を伴う場合
服用方法
通常、煎じ薬として1日1回~2回服用します。市販のエキス顆粒を利用する場合は、パッケージの指示に従って服用してください。服用前には必ず専門家(漢方医や薬剤師)のアドバイスを受けることをお勧めします。
注意点
銀翹散は主に熱を冷ます効果が強いため、寒邪のみで熱がない場合には適さない場合があります。寒気が強く、汗をかいていない場合には、他の処方(例えば葛根湯など)が適している可能性があります。服用前に専門家に相談することをおすすめします。
ツボ治療の配穴
合谷(ごうこく)
場所:手の甲側、親指と人差し指の骨が交差する部分。
効果:発熱や喉の痛みなど、上半身の症状を繰り返します。
曲池(きょくち)
場所:肘を曲げた時のシワの外端。汗法が有効。
効果:体内の熱を取り込み、炎症を和らげます。
外関(がいかん)
場所:手首から指3本分上の腕の外側。
効果:風邪の初期症状や体の熱を取り込み、免疫力を高めます。
天突(てんとつ)
場所:喉の下、鎖骨の間の窪み。
効果:喉の腫れや痛み、咳をする。これらの症状があるなら。
食べたら良い食材
熱を冷ます食材
大根、白菜、梨
喉や呼吸器を潤し、体の熱を逃がします。
豆類
緑豆(リョクトウ)
清熱解毒効果があり、風熱の症状を改善する。
果物
スイカ、梨、柿
これらは熱を冷まし、喉の冷えを癒す。
その他
ミントや菊花茶:熱を冷まし、喉をすっきりさせる効果があります。

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
入浴
初期の段階は、41~43℃程度の熱めのお湯に浸かり、体を温める。発汗することを目的とする。
症状が長引いているときは、体力を消耗するので入浴はあまりすすめない。
適度な休息
体力を回復させるために十分な睡眠を確保。 特に夜更かしは避け、早めにお休みください。
水分補給
温かいお茶や白湯を少量ずつ丁寧に飲みます。喉の乾燥を防ぎます。
日光浴
日中に10~15分程度の日光で、免疫力を高めます。
適度な運動
回復した後、軽い体調ストレッチや深呼吸を行うことで気血の巡りを良くする。
環境の工夫
部屋を加湿して乾燥を防ぎます。喉に負担をかけず、空気を清潔に保ちます。換気も必要。
まとめ
銀翹散は、風寒による風邪の状態に非常に効果的です。温める食材やツボ治療、生活習慣の改善を組み合わせることで、より効果的な治療が期待できます。