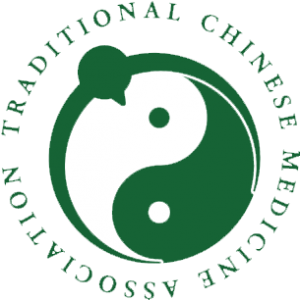麻杏甘石湯
体質:風湿邪が肺に侵入した状態
中医学では、風邪は外邪(外から体に侵入する病因)の一つで、特に肺を攻撃しやすいとされています。この場合、肺が正常に働かなくなり、感冒(風邪)や咳、頭痛などの症状を引き起こします。風邪による疾病は、前頭部や全体的な患部に痛みとして現れることが多く、発熱、咳、鼻づまり、喉の痛みなどが伴うことがあります。風邪がさらに肺に影響を及ぼすと、咳や喘息、胸の圧迫感、痰が多くなることがあります。このような症状には、「麻杏甘石湯」という漢方薬が効果的です。
おすすめ処方:麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)
麻杏甘石湯は、清熱(体内の余分な熱を冷ます)、肺を開いて呼吸を楽にする、咳を鎮めるといった効果を持つ代表的な処方です。風邪による肺の炎症や頭痛、咳に用いられます。以下に処方の構成生薬とその役割を解説します。
生薬とその効果
1. 麻黄(まおう)
→ 発汗作用を持ち、寒邪を追い払い、肺を開いて気道を楽にします。喘息や咳の改善に役立ちます。
2. 杏仁(きょうにん)
→ 咳を鎮め、気道の痰を除去し、呼吸を楽にします。特に痰が絡む咳や呼吸困難に効果があります。
3. 石膏(せっこう)
→ 強い清熱作用があり、肺の炎症を抑え、発熱や口渇を改善します。また、炎症による咳や喘息にも効果を発揮します。
4. 甘草(かんぞう)
→ 諸薬を調和し、咳を鎮め、喉の痛みや炎症を緩和します。また、他の生薬の効果を補強する役割も果たします。
適応症と使用方法
適応症
風邪による発熱、頭痛、咳、喘息、胸の圧迫感
肺の熱が強くなったことで現れる乾いた咳や痰の多い咳
鼻づまりや喉の痛みを伴う症状
服用方法
上記の生薬を適量で配合し、煎じて服用します。通常、1日1剤を2~3回に分けて温服します。
市販のエキス顆粒を使用する場合は、パッケージの指示に従って服用してください。
注意事項
1. 麻杏甘石湯は熱を冷ます効果が強いため、寒証の初期症状には適しません。その場合は、桂枝湯や麻黄湯などの温性処方を検討してください。
2. 汗を出す作用があるため、体力の弱い方や大量の汗をかいている方は慎重に使用する必要があります。
3. 服用後も症状が改善しない、または悪化する場合は、速やかに中医師や医療専門家に相談してください。
ツボ治療の配穴
1. 天突(てんとつ)
場所:喉の下、鎖骨の間の窪み。
効果:呼吸の不調を整え、咳や喘息を抑える。
2. 尺沢(しゃくたく)
場所: 肘の内側、シワの外端。
効果:肺の熱を冷まし、咳や息苦しさを緩和する。
3. 肺兪(はいゆ)
場所:背中の第3胸椎の下、左右。
効果:肺機能を改善し、咳や咳を軽減します。
4. 中府(ちゅうふ)
場所:鎖骨下、肩のやや内側。
効果:肺の気を巡らせ、呼吸の通りを良くする。
食べたら良い食材
1. 肺を潤す食材
梨、大根、山芋、蓮根
これらは肺の気を補います。
2. 豆類
緑豆(リョクトウ)、小豆
清熱解毒作用があり、肺熱の症状を緩和する。
3. 果物その他
スイカ、パチュリ
熱を冷まし、喉や肺の燥湿効果があります。
4. お茶
菊花茶、ミント茶、杏仁
肺のリラックス熱を冷まし、効果を促進します。

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
1. 入浴
38~39℃のぬるめのお湯に浸かり、体全体の皮膚呼吸を促します。
2. 水分補給
過度の摂取は良くないです。
3. 日光浴
日中に10~15分程度の日光で免疫力を高めます。 適度な日光は体の気血の流れを良くする。
4. 軽い運動
気功や深呼吸を取り入れて肺の機能を改善する。肺からの湿気感が無くなるとよい。
5. 空気の清浄化
部屋を除湿して適度な湿度を保つ。
6. 食事の注意点
辛い食べ物や脂っこい食べ物を気にする。これらは肺熱を悪化させる可能性がある。
まとめ
麻杏甘石湯は、邪気が体内の気血の流れを阻害してさらに身体の熱が排出できない状態に非常に効果的です。温める食材やツボ治療、生活習慣の改善を組み合わせることで、より効果的な治療が期待できます。