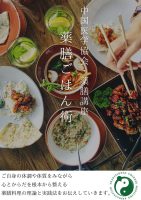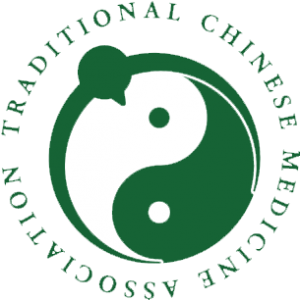竜胆瀉肝湯
体質:肝火上炎による
肝火上炎は、肝の火熱が過剰になり、上昇して患部に影響を及ぼす状態です。肝は体内で血を貯蔵し、気血の巡りを調整する役割がありますが、過剰なストレスや感情の抑圧(怒りなど)によって肝の火が燃え上がると、血が患部に過剰に巡り、疾病を引き起こします。
このタイプの疾病は次のような特徴があります:
頭がズキズキ痛む
頭部の熱感、顔のほてり
目の充血、目の痛み
イライラ、怒りっぽい
口の苦み、喉の渇き
睡眠の質が悪い(多夢、不眠)
おすすめ処方:竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)
竜胆瀉肝湯は、肝火を鎮め、湿熱を取り除く(清肝瀉火・清熱利湿)効果を持つ処方です。肝火が過剰になったことで生じる症状、特に頭痛や目の症状に対して非常に効果的です。
生薬とその効果
1. 竜胆(りゅうたん)
→ 清熱瀉火(熱を冷まし、火を抑える)。肝と胆の火を鎮める主薬。
2. 黄芩(おうごん)
→ 清熱燥湿(熱を冷まし、湿を除く)。肝火と湿熱を取り除きます。
3. 山梔子(さんしし)
→ 清熱瀉火(熱を冷まし、火を抑える)。肝火を沈静化し、目の充血や痛みを改善。
4. 沢瀉(たくしゃ)
→ 利水滲湿(水分を排出し、湿を除く)。湿熱を排出することで頭痛を軽減。
5. 木通(もくつう)
→ 清熱利湿(熱を冷まし、湿を除く)。体内の余分な湿気と熱を排出します。
6. 当帰(とうき)
→ 養血活血(血を養い、血流を促進)。肝血を補充し、血の滞りを改善。
7. 生地黄(しょうじおう)
→ 清熱涼血(熱を冷まし、血を潤す)。肝火を冷まし、血を潤します。
8. 柴胡(さいこ)
→ 疏肝解鬱(肝の気を流し、抑圧を解く)。肝の気滞を緩和し、イライラを軽減。
9. 甘草(かんぞう)
→ 調和諸薬(他の生薬の効果を調整)。薬全体のバランスを整えます。
10. 地黄(じおう)
→ 補陰清熱(陰を補い、熱を冷ます)。肝火を冷ましつつ陰を養います。
適応症と使用方法
適応症
肝火上炎による頭痛(特に感情の変化が引き金)
目の充血や目の痛み
顔のほてり、イライラ
口の苦み、喉の渇き
服用方法
生薬を煎じて1日2~3回服用。
市販のエキス顆粒を使用する場合は、添付文書に従ってください。
注意事項
1. この処方は熱や火の強い症状を対象としており、冷えが主体の症状には適しません。
2. 長期間の服用は避け、症状が改善したら中止するのが望ましいです。
3. 妊娠中や授乳中の方は、専門医の指導を受けて使用してください。
竜胆瀉肝湯の解説
竜胆肝湯は、主に肝火や肝胆の湿熱による症状を改善するための漢方処方です。 肝火とは、肝臓に過剰な熱が生じた状態で、ストレスや感情の乱れ、食生活の偏りなどこの熱が全身に影響を与えると、目の充血、耳鳴り、口痛、頭痛、怒りっぽさなどの症状が現れます。また、湿熱が重なると排尿障害や下半身のむくみなどの症状もございます。
ツボ治療の配穴
太衝(たいしょう)
位置:足の甲、親指と人差し指の骨の間、やや足首寄りの部分。
効果:肝臓の機能を整え、肝火を鎮める。感情の安定にも効果的。
方法:左右の太衝を指圧または温灸で刺激する。
陽陵泉(ようりょうせん)
位置:膝の外側下部、腓骨頭前下方のくぼみ。
効果:肝胆の湿熱を取り除き、肝胆の働きを助ける。
方法:やや強めに押しながらマッサージ。
行間(こうかん)
位置:足の甲、親指と人差し指の間のつけ根部分。
効果:肝火を冷まし、イライラや目の充血を改善する。
方法:円を描くように優しく指圧する。
曲泉(きょくせん)
位置:膝を曲げたとき、膝の内側にできるくぼみ。
効果:湿熱を取り除き、肝臓を補助する効果。
方法:軽く押し込むように指圧。
食べたら良い食材
おすすめ食材
清熱作用のある食材
緑豆、きゅうり、苦瓜(ゴーヤ)、トマト、セロリ、梨、大根おろし。
効果:体内の余分な熱を冷まし、肝火を和らげます。
肝臓の働きを助ける食材
シジミ、ほうれん草、春菊、桑の実、黒ゴマ。
効果:肝臓を養い、血流を改善する。
利尿作用のある食材
冬瓜、とうもろこしのひげ茶、ハトムギ、アスパラガス。
効果:湿熱を取り除き、体内の老廃物を排出する。
避けるべき食材
辛いもの、脂っこいもの、アルコール、甘い物などの刺激物は肝火を悪化させるため控える。

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
入浴
温浴:37~39℃のぬるめのお湯で全身をリラックスさせます。
薬湯:菊花や緑茶を布袋にいれて浴槽に続けると、肝火を冷やし気分を落ち着ける効果があります。
運動
リラックス重視:ヨガ、太極拳、ストレッチなど、ゆったりとした運動を行います。
頻度:週3~4回、1回30分程度を目安に。ストレス発散を意識。
日光浴
朝のやわらかい日を差し込むことで自律神経を整える。
方法:1日15~20分程度、朝の散歩がおすすめ。
ストレスケア
リラクゼーション:深呼吸や瞑想を日常に取り入れ、心を穏やかに。
趣味と自然とのふれあいを大切にし、心身の緊張をほぐす。
睡眠
十分な睡眠を確保し、特に夜23時~3時の時間帯に睡眠をとることが重要です。
この時間帯は肝臓が血を回復し、体を修復する時間です。
まとめ
竜胆肝湯の使い方と生活習慣の改善を知って、肝火を抑え、体内のバランスを整えましょう。