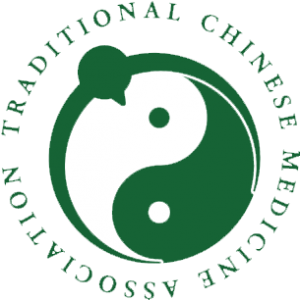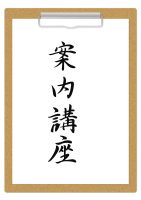茵蔯五苓散
患者の体質解説:肝胆湿熱
肝胆湿熱とは、肝臓と胆の機能が湿熱によって乱される状態で、体内の水湿が滞り、熱がこもることによって引き起こされます。この体質は、暴飲暴食、脂っこい食事、アルコール摂取、ストレスの影響で悪化するあります。主な症状は、脇腹の張りや痛み、黄疸(皮膚や目が黄色くなる)、苦い口の味や口渇、食欲不振、吐き気、尿が濃い黄色い、軟便や下痢、舌苔が黄色く厚く、舌質が紅い。
治療方針
清熱利湿:体内の熱と湿気を取り除く
疏肝胆:肝臓の気を疏通させ、胆の機能を改善する
おすすめの漢方処方:茵蔯五苓散
処方構成と生薬の役割
茵陳蒿(いんちんこう)
清熱利湿、黄疸を解消し、肝胆の熱を取り除く。
沢瀉(たくしゃ)
利尿作用があり、かなりな湿気を排出する。
猪苓(ちょれい)
水分代謝を助け、むくみを軽減します。
茯苓(ぶくりょう)
胃脾臓を補いながら水湿の滞りを解消します。
桂枝(けいし)
血行を促進し、水分代謝を改善する。
白朮(びゃくじゅつ)
脾臓を強化し、湿気の発生を防ぎます。
注意事項
体が冷えている場合は注意
湿熱を忘れて処方しますが、体が急激に冷えている場合は適さないことがあります。
長期服用の注意事項のご使用は避け、医師の指導の下で調整してください。
妊娠中は慎重に。妊婦の場合は必ず医師にご相談ください。
ツボ治療の配穴
期門(きもん)
肝臓の気を調整し、肝胆湿熱の症状を緩和します。
胆兪(たんゆ)
胆の機能を改善し、肝胆汁を促進します。
陰陵泉(いんりょうせん)
水湿を取り除き、清熱利湿の効果があります。
中脘(ちゅうかん)
胃腸の調子を整え、消化機能を助けます。
陽陵泉(ようりょうせん)
胆の経絡を刺激し、肝胆の機能を高めます。
食べたら良い食材
清熱利湿の食材
ゴーヤ、キュウリ:体を冷やし、熱を逃がす
セロリ:清熱効果があり、気を整える
緑豆、ハトムギ:湿気を取り除き、むくみを改善
冬瓜:利尿効果があり、体内の安心な水分を排出
肝を補う食材
菊花、ミント:肝臓の気を疏通す、気分を落ち着ける
柑橘類(レモン、オレンジ): 肝臓の気を調整する
避けるべき食材
油っこいもの、辛いもの、アルコール
甘いもの(湿を悪化させる)

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
入浴
ぬるめ(38~40℃)の温浴を15~20分
汗を軽くかく程度で、過剰に熱を加えませんようにします。
菊花や薄荷(ミント)の入浴剤を使用して
清涼感を得ながら、肝臓の熱を冷やします。
運動
やウォーキングストレッチ
激しい運動よりも、気を整えるゆったりとした運動が効果的です。
ヨガや太極拳
ストレス緩和と気血の巡りを改善します。
日光浴
午前中に穏やかな日差しを差し込む(10~15分)
自律神経を整え、肝臓の機能を改善します。
まとめ
茵蔯五苓散は、肝胆湿熱による症状を緩和するのに効果的な処方です。食事と生活習慣の見直しを組み合わせて、清熱利湿と疏肝利を促進することで、症状の改善が期待できます。