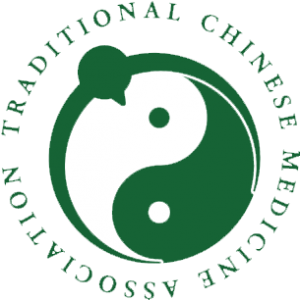黄耆建中湯
体質:胃の湿熱による
患者は胃に湿熱(湿気と熱の邪気)が蓄積しており、その影響が胃経(胃の経絡)を通じて患部に伝わり、気血が滞ることで疾病が発生しています。湿熱は気の流れを妨げ、気滞や血瘀(血の停滞)を引き起こすため、患部の膨張感や圧迫感を伴うことが多いです。また、湿熱は消化器官に影響を与えるため、口の渇き、食欲不振、口内炎、胃の重だるさなども併発する可能性があります。
おすすめ処方:黄耆建中湯(おうぎけんちゅうとう)
黄耆建中湯は、胃腸の機能を強化し、気血を補いながら、体内の湿熱を除去する働きを持つ処方です。湿熱による胃経の不調を改善し、気血の流れを整えることで頭痛を含む症状を緩和します。
生薬とその効果
1. 黄耆(おうぎ)
→ 補気益気(気を補い、免疫力を高める)。胃腸の機能を強化し、湿熱の排出を助けます。
2. 桂枝(けいし)
→ 温経通陽(経絡を温め、血流を促進)。気血の循環を改善し、滞りを解消します。
3. 芍薬(しゃくやく)
→ 緩急止痛(筋肉の緊張を和らげ、痛みを緩和)。胃経の筋肉の緊張をほぐします。
4. 大棗(たいそう)
→ 補中益気(胃腸を温め、機能を補助)。体力を回復し、湿熱を改善します。
5. 生姜(しょうきょう)
→ 散寒除湿(冷えと湿気を取り除く)。湿熱を整え、気の流れをスムーズにします。
6. 甘草(かんぞう)
→ 調和諸薬(他の生薬のバランスを整える)。胃腸を保護し、全体的な効果を高めます。
適応症と使用方法
適応症
胃の湿熱による頭痛
食欲不振、口内炎、胃の重だるさ
体力の低下や疲労感
服用方法
生薬を煎じて、1日2~3回に分けて温服します。
市販のエキス顆粒を使用する場合は、添付の指示に従って服用してください。
注意事項
1. 寒性の体質や冷え性の方には慎重に使用する必要があります。
2. 妊娠中の方や持病のある方は、使用前に医師に相談してください。
3. 湿熱の症状が強い場合は、併せて食事や生活習慣の改善が重要です。
解説
黄耆建中湯は、胃の湿熱を改善し、胃経を通じた頭部の気血の滞りを解消する処方です。湿熱による胃腸の負担を軽減し、気血の循環を整えることで、痛みや関連する症状を効果的に緩和します。
黄耆建中湯の適応と効果
黄耆建中湯は、体内の寒湿邪(寒さと湿気の邪気)が胃経に侵し、消化機能の低下や腹部の冷え、胃痛、倦怠感などの症状に適応します。気血を補い、体を温め、腸を保護する効果があります。 特に寒湿邪を排除しつつ、虚弱な体質を改善します。
ツボ治療の配穴
1.中脘(ちゅうかん)
場所:おへその上4寸(約指幅4本分)。
効果:胃腸を温め、寒湿を取り除き、消化機能を整える。
2. 気海(きかい)
場所:おへその下1.5寸(約指幅1.5本分)。
効果:体のエネルギー(気)を補充し、胃腸を温める。
3. 足三里(あしさんり)
場所:膝のお皿の下、外側にある窪み。
効果:胃腸の機能を強化し、気血を補う。による胃痛にも効果的。
4. 脾俞(ひゆ)
場所:背中の第11胸椎の視野。
脾効果:胃の機能を整え、寒湿邪を追い出す。
5. 関元(かんげん)
場所:おへその下3寸(約指幅3本分)。
効果:体を温め、胃腸の冷えを改善。
食べたら良い食材
体を温め、消化を助ける食材
ショウガ:胃腸を温め、寒湿を追い出す。ショウガ湯やスープに続けて良い。
山芋:胃腸を強化し、消化を助ける。蒸すかスープに続きます。
ネギ:体を温め、寒湿邪を排除する。スープや炒め物に使います。
鶏肉:気血を補い、胃腸を温める。生姜と一緒に煮込むと効果的。
黒胡椒:温める作用があり、寒邪を除去する。スープや料理の調味料として使用。
紅茶:温性飲料として寒湿邪を改善します。
避けるべき食材
冷たい飲み物や生野菜(胃腸を冷やして症状を悪化させる可能性あり)。
脂っこいものや辛すぎる食べ物(腸に負担をかける)。

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
入浴
温浴(40〜42℃)で体全体を温める。冷えが強い場合は、ショウガやヨモギを加えたお風呂が良い。
お腹や腰を中心に温めると腸の血流を促進し、寒湿を排除しやすくなります。
運動
激しい運動は避け、軽いストレッチや散歩が効果的です。
ヨガや気功を行い、気血の循環を促進する。
日光浴
朝の穏やかな陽光を15〜20分浴びることで、体を温め、気の巡りを良くします。
特に背中お腹を太陽に襲うと効果的。
その他の注意事項
保温:腹部や腰、足元を冷やさないように工夫する。 特に夜間は湯たんぽを使うと良い。
規則正しい生活:毎日決めた時間に食事を取り、胃腸の負担を軽減します。
十分な休息:胃腸の機能回復には、無理をせずに十分に休むことが大切です。
まとめ
黄耆建中湯は、胃腸の冷えや寒湿邪による不調を改善します。ツボ治療や食事療法、生活改善を取り入れることで、さらに体調が整いやすくなります。