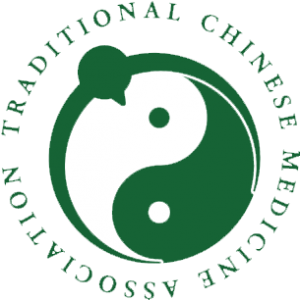茵蔯蒿湯
体質:脾胃湿熱により気血の流れが重たい(湿熱内盛、気滞血瘀)
患者は「脾胃湿熱」の状態にあります。湿熱が脾胃に停滞すると、消化機能が低下し、湿が体内に溜まります。この湿邪が患部に影響を及ぼすことで、ズーンと重たい感覚の痛みや症状が引き起こされます。また、湿が気の流れ(気機)を阻害することで気滞が生じ、気血の巡りが悪化し、「不通則痛」(通じなければ痛む)として痛みが発生します。このタイプの患者は、頭痛、食欲不振、胸のつかえ感、口の苦み、全身の重だるさなどの症状を伴うことが多いです。
おすすめ処方:茵蔯蒿湯(いんちんこうとう)
茵蔯蒿湯は、脾胃の湿熱を清熱利湿する処方で、湿と熱が原因となる症状に対応します。湿熱を取り除くことで、患部の疾患の原因となる気滞と血瘀を解消します。
生薬とその効果
1. 茵蔯蒿(いんちんこう)
→ 清熱利湿(熱を冷まし湿を取り除く)。湿熱による脾胃の停滞を改善します。
2. 山栀子(さんしし)
→ 清熱瀉火(熱を冷まし、余分な火を下ろす)。体内の炎症や熱感を和らげます。
3. 大黄(だいおう)
→ 瀉熱通便(熱を下げ、便通を促す)。体内の熱を排出し、湿熱の解消を助けます。
適応症と使用方法
適応症
脾胃湿熱による重たい頭痛
胃の不快感、食欲不振
体の重だるさ、胸のつかえ感
口苦(口の中が苦い)、尿が黄色く濃い
服用方法
生薬を煎じて、1日2~3回に分けて服用します。
市販のエキス顆粒を使用する場合は、添付文書に従ってください。
注意事項
1. 胃腸が非常に弱い方は、大黄が刺激を与える場合があるため、医師に相談してください。
2. 長期間の服用は避け、症状が改善したら使用を中止してください。
3. 妊娠中や授乳中の方は使用を控えるか、専門医に相談してください。
解説
茵蔯蒿湯は、湿熱が原因で起こる症状に特化した処方です。湿熱を解消することで、気滞や血瘀を改善し、患部の病変の根本原因を取り除きます。また、脾胃を整えることで、湿熱の再発を予防します。この処方は特に湿熱が疾病の主因となる患者に効果的で、体全体の湿邪を取り除く効果も期待できます。
茵蔯蒿湯について
茵蔯蒿湯(いんちんこうとう)は、湿熱の邪気が体内、特に脾臓胃に滞留している状態に置く漢方処方です。湿熱を取り除き、体内の気血の流れを改善する効果がこの湿熱が長引くと気滞血瘀を我慢し、さらに体調を悪化させる原因になります。
ツボ治療の配穴
以下のツボは、湿熱を取り除き、気血の流れをスムーズにするために有効です:
中脘(ちゅうかん)
位置:おへそから指4本分の位置
脾臓効果:胃の機能を高め、湿熱を改善する。
方法:軽い圧力で5分ほどマッサージ。
足三里(あしさんり)
位置:膝のお皿の下、指4本分下のくぼみ。
効果:脾臓を強化し、消化機能と気血の循環を促進する。
方法:片方ずつ3分ずつ押圧。
陰陵泉(いんりょうせん)
位置:膝の内側、脛骨の縁にあるくぼみ。
効果:脾臓の湿気を取り除く効果、下半身のむくみや重だるさを軽減する。
方法:ゆっくりと圧力を加え、指圧を3分程度。
太白(たいはく)
位置:足の内側、親指の付け根の骨のくぼみ。
効果:脾臓を補い、消化吸収を助ける。
方法:軽く押して刺激する。
食べたら良い食材
湿熱を改善し、脾臓胃を強化する食材を摂取することが効果的です。
おすすめの食材
清熱効果のある食材
きゅうり、冬瓜、セロリ、大根、ゴーヤ、レンコン。
→体内の安心な熱を取り除きます。
利湿効果のある食材
緑豆、とうもろこしのひげ茶、小豆、はとむぎ。
→湿気を排出し、むくみを解消します。
胃腸に優しい食材
山薬(ヤマイモ)、カボチャ、ほうれん草、クコの実。
→ 胃腸の機能を高めながら、湿熱を抑えます。
避けた食材
油っこいもの、甘すぎるもの、アルコール、辛味が強いもの。
→湿熱を悪化させる可能性があります。

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
入浴湿熱の症状には、熱すぎない温めの湯(38~40℃)で15~20分程度浸かり、体内の循環を温めます。
生姜を少量湯船に入れると、湿気を追い出しやすくなります。
運動軽いストレッチやヨガを取り入れることで、気血の流れを良くします。
特に「体をひねるポーズ」は脾臓の循環を改善します。
週3~4回のウォーキング(30分程度)が効果的です。
日光浴朝のやわらかい日差しを10~15分浴びることで、気の流れを整えます。湿気を軽減し、体のバランスを整えます。
生活リズムの改善
規則的な食事と睡眠を心がけ、遅い時間の飲食を気にすることで脾臓を保護する。
スマホやテレビなどの画面を寝る前に見すぎないように、心身をリラックスさせます。
まとめ
茵蔯蒿湯の処方と合わせて、これらの生活改善と食事療法を取り入れることで、湿熱の改善がさらに促進され、全体的な健康状態が向上します。