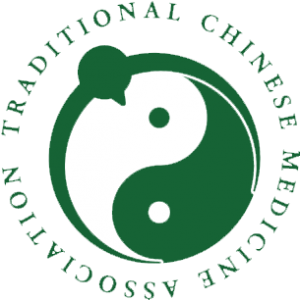四物湯
体質:貧血(血虚)による
血虚(血液不足)が原因で気血の巡りが悪くなり、患部への十分な栄養供給ができなくなっています。このため、経絡の通りが滞り、「不通則痛」(通じなければ痛む)として痛みが生じています。血虚の状態では、顔色が蒼白または黄色く艶がなく、疲労感、めまい、ふらつき、動悸、不眠などを伴う場合があります。特に女性では月経不順や経血の減少も見られることがあります。
おすすめ処方:四物湯(しもつとう)
四物湯は、血を補い、血行を促進する効果がある、血虚を改善する基本的な処方です。この処方は血液の生成を助け、滞った血を動かして経絡を通じさせるため、貧血による痛みを緩和します。
生薬とその効果
1. 当帰(とうき)
→ 補血活血(血を補い、血行を促進する)。血虚による頭痛や冷え性を改善します。
2. 川芎(せんきゅう)
→ 活血行気(血行を良くし、気を巡らせる)。頭部の血流を改善し、痛みを緩和します。
3. 芍薬(しゃくやく)
→ 養血柔肝(血を補い、筋肉をリラックスさせる)。頭痛や筋肉の緊張を和らげます。
4. 熟地黄(じゅくじおう)
→ 滋陰補血(血を増やし、体を潤す)。血虚による乾燥感や虚弱体質を改善します。
適応症と使用方法
適応症
貧血による頭痛
疲労感、めまい、顔色の悪さ
月経不順や経血の減少(女性の場合)
服用方法
生薬を煎じて、1日2回に分けて服用します。
市販のエキス顆粒を使用する場合は、添付の指示に従って服用してください。
注意事項
1. 消化機能が弱い方は、四物湯が胃腸に負担をかける場合があるため、医師に相談してください。
2. 長期間服用する場合、定期的に医師の診断を受けてください。
3. 妊娠中や持病のある方は、専門医に相談してください。
四物湯の解説
四物湯(しもつとう)は、血虚(けっきょ)の改善に用いられる基本的な漢方処方です。血虚とは、血液の不足や栄養の供給不足により、皮膚の乾燥、めまい、疲労、この処方は養血作用を中心に、血液の循環を改善し、全身の調和を保つ効果があります。
ツボ治療の配穴
血海(けっかい)
位置:膝の内側、膝蓋骨の内側上部から指3本分上。
効果:血を補い、血液循環を促進する。
方法:指の腹で優しく指圧します。
足三里(あしさんり)
位置:膝蓋骨の下、指4分外側の位置。
効果:全身の気血を補い、疲労感を緩和する。
方法:ゆっくり押圧し、温灸も効果的。
三陰交(さんいんこう)
位置:足首の内側、内くるぶしの上、指4本の上の位置。
効果:脾臓・肝臓・腎臓を強化し、血を養う。
方法:心地よい強さで刺激を考える。
膈兪(かくゆ)
位置:背中の第7胸椎の真ん中、背骨の左右。
効果:血を補い、血液循環を促進します。
方法:軽い指圧や温灸。
食べたら良い食材
養血の食材
血を補う食品
黒ゴマ、クコの実、なつめ、鶏肉や牛肉。
効果:血液の栄養を補い、血虚を改善します。
血の材料の多い食品
レバー、ほうれん草、ひじき、小松菜。
効果:血液を作るための鉄分補給。
温性の食品
生姜、山芋、かぼちゃ。
効果:体を温め、血液の循環をサポート。
気血を補う食品
サツマイモ、大豆、黒糖。
効果:エネルギーを補い、疲労回復。
避けるべき食品
冷たい飲み物や食事(アイス、冷えた果物など)。
辛すぎるものや脂っこいもの。

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
入浴
温浴リラックス:38~40℃のぬるめのお湯で20分程度。
薬湯:ヨモギ、当帰、ショウガを布袋にいれて浴槽に続けると血行促進効果が高まります。
運動
筋量を増やすようなスロートレーニング:スクワットや軽い筋トレも効果的です。
軽い有酸素運動:ウォーキング、太極拳、ヨガなどを1日20~30分行います。
ストレッチ:筋肉を柔軟に、血液、循環を促進します。
日光浴
毎朝10~15分程度、太陽光でビタミンDの生成を促進します。血液循環の改善につながります。
睡眠
夜22時~23時までには就寝し、7~8時間の睡眠を確保します。血液の生成と体の回復を助けます。
ストレス管理
瞑想や深呼吸、趣味の時間を確保して心身の調和を保つ。
まとめ
四物湯は血虚を改善する基本的な処方であり、正しい食事や生活習慣、ツボ治療と言うことで、より早い改善が期待できます。