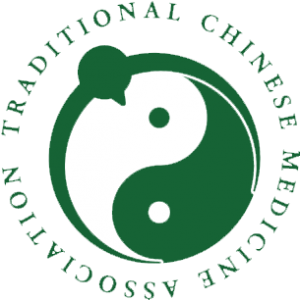二朮湯
体質:湿熱証による
湿熱証は、体内に湿気と熱が結びついて滞り、正常な気血の流れを妨げる状態です。この場合、むくみによって気血が停滞する一方、熱が無理やり気血を巡らせようとするため、患部に不自然な負担がかかり、疾病が発生します。
湿熱による疾病の特徴は以下の通りです:
頭が重く、締め付けられるような痛み
悪心やだるさを伴うことが多い
顔色が赤く、皮膚が湿った感触
口の渇きがあるが、水を飲むと胃が重くなる
舌苔は黄くてべたつき、脈は滑数
おすすめ処方:二朮湯(にじゅつとう)
二朮湯は、湿熱を取り除き、気血の流れを改善するための処方です。この処方は、特に脾胃の湿熱を調整し、全身の気血循環を正常化することで、痛みやむくみを解消します。
生薬とその効果
1. 蒼朮(そうじゅつ)
→ 燥湿健脾(湿を乾かし脾を強化)。体内の余分な湿を除去し、脾胃の機能を高めます。
2. 白朮(びゃくじゅつ)
→ 補脾益気、利水滲湿(脾を補い気を増やし、余分な水分を排出)。むくみを改善します。
3. 茯苓(ぶくりょう)
→ 健脾利水(脾を助け水分代謝を促す)。湿熱の蓄積を解消し、消化機能を改善。
4. 猪苓(ちょれい)
→ 利水滲湿(体内の余分な水分を除去)。湿を排出し、むくみを改善。
5. 黄芩(おうごん)
→ 清熱燥湿(熱を冷まし湿を乾かす)。体内の湿熱を取り除き、炎症を抑えます。
6. 沢瀉(たくしゃ)
→ 利水滲湿(余分な水分を排除)。むくみを改善し、湿熱を除去します。
7. 陳皮(ちんぴ)
→ 理気健脾(気の流れを整え、脾を助ける)。気滞を解消し、湿の停滞を改善。
8. 半夏(はんげ)
→ 燥湿化痰(湿を乾かし痰を解消)。頭部の重さを軽減し、気血の流れを促進します。
適応症と使用方法
適応症
湿熱証による頭痛
顔のむくみ、全身の倦怠感
胃の重さ、悪心、口の苦み
舌苔が黄くべたつく
服用方法
生薬を煎じて服用する場合、1日2回(朝・夜)に分けて服用します。
エキス剤の場合は、1日2~3回、食前または食間に服用します。
注意事項
1. 体質が冷え性の場合、この処方の使用は避けてください。湿熱に特化した処方であり、寒証には適しません。
2. 湿熱証の改善が見られた後、長期服用は避けてください。
3. 胃腸が極端に弱い方や妊娠中の方は、専門医の指導のもとで使用してください。
二朮湯の解説
二朮湯は、湿熱証による気血の滞りを解消し、全身の機能を回復させる処方です。湿熱が脾胃を犯している場合に有効であり、むくみや重だるさ、頭痛の根本的な原因を取り除きます。また、湿熱を取り除きつつ気血を調整するため、体全体のバランスを整える効果があります。
注意事項
服用方法
食間温かいお湯で飲むと吸収が良いです。
湿熱の解消には継続的な摂取が必要です。
副作用
体質によって胃腸が刺激を感じる場合があるため、異常があれば医師に相談してください。
禁忌
体が冷えている場合や実熱がない場合には使用を恐れる。
妊娠中の方は、服用前に医師に相談します。
ツボ治療の配穴
湿熱を除去する主要なツボ
中脘(ちゅうかん)
位置:みぞおちとへその中間
効果:胃の運化を助け、湿熱を除く。
方法:指圧や軽いお灸。
足三里(あしさんり)
位置:膝蓋骨の下、指4分下の外側。
効果:胃腸を整え、気血の流れを促進します。
方法:指圧または温灸。
陰陵泉(いんりょうせん)
位置:膝の内側、すねの骨の外側。
効果:湿気を排出し、利水作用を強化します。
方法:軽く温めるか温める。
脾兪(ひゆ)
位置:背中、背骨の視野、第11胸椎の下。
効果:脾を補い、利湿効果を包括します。
方法:温灸や軽いマッサージ。
豊隆(ほうりゅう)
位置:すねの外側、足首の上8cm。
効果:痰湿を取り除き、効果的な脾胃機能を改善します。
方法:軽い指圧。
食べたら良い食材
化湿と清熱に良い食品
利湿食材
ハトムギ(ヨクイニン)、冬瓜、きゅうり、セロリ。
効果:利尿作用を促進し、体内の余分な水分を排出します。
清熱作用のある食材
緑豆、大根、苦瓜(ゴーヤ)、白菜。
効果:体内の熱を冷まし、炎症を和らげます。
胃腸を整える食材
サツマイモ、山薬(ヤマイモ)、レンコン。
効果:胃腸の働きを助ける。
デトックス効果のある飲み物
薄い緑茶、菊花茶、プーアル茶。
効果:体内の熱と湿気を解消します。
その他のおすすめ
魚(白身魚)、鶏むね肉(脂肪)
効果:消化に優れ、栄養を補う。
避けるべき食品
油っこい食べ物、甘いもの、乳製品(チーズ、バターなど)。
冷たい飲み物や生野菜(胃腸にかかる)。

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
入浴
温浴:38~40℃のぬるめのお湯に15~20分浸かる。湿熱を緩和するため、長湯はあまりおすすめしません。
薬湯:ハトムギや生姜を使った入浴剤を入れて、体内の念入りな湿気を排出します。
運動
軽い運動:ウォーキングやストレッチ。湿熱が強くのぼせなどがきつい時は、激しい運動など無理をしないように。
呼吸法:腹式呼吸を取り入れ、気の流れを整える。
日光浴
朝の柔らかい日差しを10~15分浴びる。 特に胃の辺りを温められるように。
今後のアドバイス
定期的に正しい食事時間を守り、胃腸を休んでください。
夜更かしを避け、十分な睡眠をとることができます。
ストレスを軽減するためにリラクゼーション法を取り入れます。
まとめ
二朮湯は湿熱を取りながら胃脾を整える効果があります。