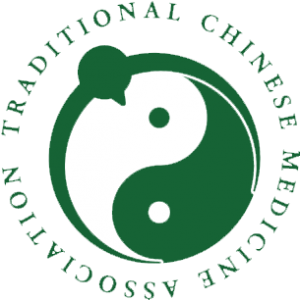六君子湯
体質:むくみと貧血(脾虚・血虚)による
患者は「脾虚」と呼ばれる状態にあり、脾の働きが低下しているため、気血の生成が不十分です。その結果、「血虚」(血液不足)を引き起こし、気血の巡りが悪化しています。また、むくみ(体内の水湿停滞)も脾の機能低下によるものです。これにより、全身の気血が患部に十分届かず、「不通則痛」(通じなければ痛む)として痛みが発生しています。このタイプの疾病は、倦怠感、胃腸の虚弱、顔色の悪さ、むくみなどの症状を伴うことが多いです。脾は運化、統血、昇清の働きがあります。脾虚になると貧血やむくみなどを引き起こすことがあります。
おすすめ処方:六君子湯(りっくんしとう)
六君子湯は、脾胃の機能を強化し、気を補い、湿を除去する効果があります。気血の生成を助け、むくみを改善しながら、全身の気血の巡りを改善するため、むくみと貧血による疾病に適しています。
生薬とその効果
1. 人参(にんじん)
→ 補気健脾(気を補い、脾を強化)。体全体のエネルギーを高め、胃腸の機能を改善します。
2. 白朮(びゃくじゅつ)
→ 健脾利水(脾を助けて水分代謝を促進)。むくみを改善し、胃腸を整えます。
3. 茯苓(ぶくりょう)
→ 健脾利湿(脾を助けて湿を除去)。体内の余分な水分を排出し、むくみを緩和します。
4. 半夏(はんげ)
→ 燥湿化痰(湿を乾かし、痰を取り除く)。消化機能を整え、胃の働きを助けます。
5. 陳皮(ちんぴ)
→ 理気健脾(気を巡らせ、脾を助ける)。胃腸の働きを促進し、消化不良を改善します。
6. 甘草(かんぞう)
→ 調和諸薬(全体のバランスを整える)。胃腸を保護し、痛みを緩和します。
適応症と使用方法
適応症
むくみと貧血による頭痛
胃腸の虚弱、食欲不振
倦怠感、顔色の悪さ
めまいや冷え性
服用方法
生薬を煎じて、1日2~3回に分けて服用します。
市販のエキス顆粒を使用する場合は、添付文書の指示に従ってください。
注意事項
1. 胃腸が過度に冷えたり弱っている方には、少量から始めることをおすすめします。
2. 妊娠中や持病のある方は、専門医に相談してから使用してください。
3. 長期間服用する場合、定期的に医師の診断を受けてください。
六君子湯の解説
六君子湯は、脾胃の働きを助けながら、気血の生成を促進する処方です。また、余分な水分を取り除く作用があり、むくみを改善することで気血の巡りを良くします。これにより、頭痛の原因である「不通」を解消し、全身の体質を整える効果が期待できます。特に、むくみと貧血が同時に起こるケースで有効な処方です。
ツボ治療の配穴
脾虚と水湿滞を改善するツボ
足三里(あしさんり)
位置:膝の外側、膝蓋骨の下、指4分下。
脾臓効果:胃を強化し、消化機能を改善します。
方法:指圧または温灸。
中脘(ちゅうかん)
位置:おへそとみぞおちの中間。
効果:胃腸の働きを活性化し、胃の不快感を軽減します。
方法:軽い指圧またはお灸。
陰陵泉(いんりょうせん)
位置:膝の内側、膝下のくぼみ。
効果:湿気を取り除き、利尿を促進します。
方法:指圧またはマッサージ。
脾兪(ひゆ)
位置:背中の第11胸椎の視野、指2本分外側。
効果:脾臓の働きを調整し、気血の流れを良くする。
方法:軽い圧力をかけます。
三陰交(さんいんこう)
位置:内くるぶしの上、指4本の高さ。
脾効果:胃を補い、全身の気血を調整。
方法:指圧または軽く揉む。
食べたら良い食材
健脾と利湿が大切
・脾臓を補う食材
そば:消化を助け、脾臓胃を元気にする。
サツマイモ:胃腸に優しく、エネルギー補給に最適。
カボチャ:脾臓を温め、消化を促進します。
・水分を追い出す利湿の食材
冬瓜:たっぷりな水分を排出し、むくみを改善。
ハトムギ:利尿を促進し、体内の湿気を和らげる。
セロリ:体を冷やし、湿気を軽減します。
・気を補うのに良い食材
大豆:脾臓を補い、全身のエネルギーを強化。
黒糖:胃腸を温め、疲労を軽減します。
・避けるべき食材
脾臓胃に負担をかける脂っこい食べ物、冷たい飲み物、甘いお菓子は控える。

おすすめレシピはこちら
今の体調を整える香り
芳香療法で気持ちも改善しよう
おすすめの芳香処方はこちら

おすすめの生活改善
・入浴
全身浴:38~40℃のお湯に15~20分ゆっくり浸かる。生姜やハーブを入れた入浴剤を使うと、体を温めながら汗で湿気を排出します。
・足湯:冷えが強い場合は足湯で下半身を温める。ジンジャー、シナモンのアロマを入れると効果的。
・運動
ウォーキング:1日30分程度の軽い運動で脾臓を刺激し、水分代謝を促進します。
ヨガやストレッチ:全身の血行を良くし、リラックスを促すポーズ
まとめ
六君子湯は、脾虚からくる湿の改善に効果的な処方です。 健脾と化湿を目的とした生活改善、食事療法、ツボ治療を併用することで、症状の改善が期待できます。定期的に体調をチェックし、必要に応じて処方を調整してください。